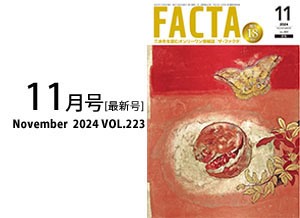連載「シン鳥獣戯画」/『吾輩は猿である』/在来種守るは人のため/松田裕之・日本生態学会元会長
2025年5月号
LIFE [シン鳥獣戯画]
by 松田裕之(日本生態学会元会長)

車道で毛繕いする屋久島猿
吾輩は屋久島猿である。世界自然遺産の島屋久島だけに棲む日本猿の亜種である。
日本猿は世界の観光客の人気者だ。下北半島の猿は人間を除く世界最北端の野生の霊長類であり、地獄谷の猿は温泉に入ることで有名だ。宮崎県幸島(こうじま)の猿は芋を洗う「文化」を群れで継承することで、世界の霊長類学者の注目を浴びた。そして、我々屋久島の猿も観光客の人気者である。
日本の霊長類学は世界的に有名だが、多くの日本の猿学者は、まず屋久島の我々を調査対象にする。屋久島には京都大学の猿学者の小屋があり、そこが彼らの研究拠点だ。

芋洗いをする宮崎県幸島の猿(京大HPより)
彼らは吾輩の敵ではなく、味方であり、理解者である。世界遺産の島、屋久島といえども、我々は果樹園を荒らす「害獣」とされ、駆除の対象となっている。2012年には1495頭が捕獲され、今でも数百頭が毎年捕殺されている。昔、体を張って捕殺部隊を阻止してくれた猿学者もいた。日本の猿学者は、我々に標識をつけたり番号で呼んだりせず、顔を覚えて個体識別し、名前を付けてくれる。すなわち、我々を人間と同格に扱ってくれる。
しかし、四半世紀ほど前の話だが、その味方の猿学者と同じ研究所の別の猿学者は、野生の鹿を食べるなら、猿も食べていいと言っていた。吾輩も、相手を見てつきあい方を考えねばなるまい。
我々猿は群れを成す。群れの中に雄も雌も複数の成獣がいて、子供もいる。雌は一生、生まれた群れで過ごすが、雄は成熟すると群れを出て、しばらく単独で暮らした後、別の群れに入ろうとする。群れの個体数が増えると2群に分かれる。
一、 「子殺し」も適応戦略

温泉に浸かる地獄谷の猿
猿の仲間でも、社会構造は千差万別である。チンパンジーは父系社会であり、雌が群れを離れる。オランウータンの多くは単独生活、ゴリラやマントヒヒは一夫多妻で、テナガザルは一夫一妻制と言われる。
マントヒヒやチンパンジーなどは群れの中で「子殺し」が起こることで有名だ。世界で最初に「子殺し」をハヌマンラングールで発見したのは1962年の当時大学院生だった杉山幸丸氏という。ただし、これは自分の実の子を殺すわけではない。一夫多妻の群れの雄が入れ替わったとき、前の雄の子を新たな雄が殺す。子を殺せばその母親が妊娠可能になり、自分の子を産ませることができる。当時はまだ種全体が繁栄することが生物の適応戦略だと考えられていた時代で、学者もマスコミも衝撃を受けたようだ。
けれども、76年の進化生物学者ドーキンスの著書『利己的な遺伝子』以後、自分の子孫を増やす行為こそが適応戦略と考えられるようになった。今では、他の種でも子殺しは知られている。さらに、ゲラダヒヒでは大集団の一夫多妻を作るが、雄が入れ替わると雌が流産し、新たな雄を受け入れる。この場合は生んでも子殺しの憂き目にあうことを未然に防ぐ母猿の適応戦略だと説明されている。
霊長類の社会は、人間に準じるものとして、人類学者が研究対象としてきた。彼らは先進国の都会に住みながら、研究のために熱帯林の奥地に入り込み、猿の棲み処に近づく。猿が罹っている風土病を彼らが持ち帰る危険がある。逆に、彼らが猿にインフルエンザなどの人間の感染症をもたらすこともある。彼らの調査指針には、野外調査における人獣共通感染症対策が欠かせない。
我々は、人間と出逢って行動を変える。鹿や熊や猪に劣らず、我々も農作物は大好物だ。人間を警戒する群れもいるが、こと屋久島では、観光客を恐れる必要はない。我々が車道にいれば車が止まる。この間は、とうとう、彼らの目の前で群れの雌が授乳し始めた。
昔は観光客が餌をくれたものだ。日光市が2000年に「サル餌付け禁止条例」を作って以来、日本各地で野生動物への餌やりを禁止する注意書きや条例や法律ができている。
我々は群れをつくるので、人なれは群れ単位で進む。日本の猿管理では、各地の群れを追跡し、個体数や分布域とともに、5段階の「加害レベル」を判定している。24年7月号の熊では、キムンカムイとウェンカムイを個体ごとに区別したが、加害レベルが4または5に進んだ猿は群れごと駆除の対象にされる。しかし、3以下の加害群は駆除対象ではなく、我々の人なれはなお進んでいるという。なお、段階の分け方やどこまで駆除対象とするかは地域ごとに工夫できる。
二、 絶滅より種間交雑が問題

下北半島の猿(文化遺産オンラインより)
我々屋久島の猿は、1998年の環境省レッドリストでは準絶滅危惧とされていたが、個体数が回復し、2007年にはランク外の普通種になった。ただし、今度は日本猿と別の猿との交雑が問題になっている。青森県下北半島と和歌山県では台湾猿と交雑していた。そちらは交雑個体を捕りきることができたようだが、千葉県では赤毛猿と交雑している。
昔の教科書にある種の定義に、雑種はできても、雑種自体は不妊で孫を作れないという条件があった。しかし、必ずしもそうではない。日本鹿は英国スコットランドで赤鹿と交雑し、赤鹿の集団に日本鹿の遺伝子が「浸透」している。在来種と外来種の生息域が重なっているある地域では、おそらく5回の種間交雑が起こり、その後は交雑個体が在来集団の繁殖に加わり、4割以上が雑種になったという報告もある。
日本猿の純系統を保全するため、純粋の赤毛猿だけでなく、交雑個体も駆除対象である。特定外来生物法では明確な規定はないそうだが、在来生物の遺伝子を撹乱することは、可能ならば避けるべきという。
人間の男は知らないが、猿の雄は、相手が同種だろうと異種だろうとあまり気にしないだろう。一夫一妻とは異なり、繁殖の機会は多いほどありがたい。雌は事情が違うかもしれない。限られた妊娠の機会の相手となる雄は、選り好みしたい。他の雌からも持てる雄を選べば、おそらくその息子も多くの雌に受け入れられ、孫を増やすことができるだろう。ただし、むしろ雌のほうが異種の異性を毛嫌いしていないという報告もある。
雌が選ぶ雄は、必ずしも生存率が高い雄や強い雄ではなく、雌に持てる雄である。自己撞着と思われるかもしれないが、要するに、多くの雌に持てる雄を自分も選ぶ方が雑種の子孫を増やしやすいということだ。逆に言えば、他の雌に選ばれない雄を選ぶと息子が苦労するかもしれない。倫理に反すると言われようが、多数派に逆らうことは損である。それが人間社会でも差別を生む温床となりえる。
これを「セクシーな雄」仮説という。選ぶ相手が、マンモスのようにおそらく無意味に大きな角を持つ雄や、一文の得にもならない髪型に凝る男でも構わない。前述の子殺しと同様に、必ずしも種全体の繁栄をもたらさない適応進化が起こりえる。これは「自然淘汰説」のダーウィン自身も指摘しており、「性淘汰」という。
話を戻そう。千葉県の日本猿と赤毛猿との交雑も深刻だ。どちらも雄が群れを離れて別の群れに入り込むため、一方の雄が他方の群れに入り込み、子孫を増やす。交雑一世は姿かたちで区別できるが、子孫になると純粋の日本猿と見た目では区別できない交雑個体がいるという。
交雑個体を駆除するのは、必ずしも猿自身の為ではない。人間に置き換えて考えればわかるだろう。意図したか否かはともかく、人間どものせいで赤毛猿や台湾猿が日本に入りこんだ。その後は野生状態で交雑が繰り返された。猿に人間と同じ権利を認めるなら、交雑個体も排除すべきではないし、「移民」にも権利を与え、受け入れることもあり得る。しかし、人間どもは野生動物に関しては自然保護と称して外来種を排除する。
日本在来のトキが多くいる時代なら、中国産のトキを入れることは考えられず、侵入してきたら排除を考えたかもしれない。しかし、数が減った後の沖縄のジュゴンではしなかったが、在来集団が絶滅寸前になっていたら、域外から迎え入れて、交雑してでも、在来の遺伝子を残そうとしたかもしれない。そしてトキが絶滅した後は、異国から再導入したトキの野生化を希望の星のように称えている。
人間とは、かように勝手な生き物である。もっとも、それが人間社会に利するということなのだろう。人間どもも生態系なくして生きてはいけない。彼らの知恵も自然を一から設計するには遠く及ばず、外来種が入った後の自然が彼らにとって快適かを判断できない。昔、沖縄本島と奄美大島に学者が意図的にマングースを導入して毒蛇のハブを退治しようとして失敗した経験もあり、彼らは保守的で、現状維持を望んでいる。また、変わりゆく生態系の変化を少しでも押しとどめようとする。台無しになった自然に対しては、手を入れて元の自然に近い生態系を勝手に創り出そうとする。
人間どもに言いたい。我々がいる自然のほうが人間を豊かにすると思うなら、「情けは他人のためならず」であり、彼らが猿の交雑個体を排除するのは勝手だ。しかし、それが猿のためだとは思わないでほしい。少なくとも外来種や交雑個体にとっては迷惑な話である。
そして、吾輩も、吾輩の利益を求めさせていただく。屋久島の農地にはおいしい柑橘類があり、吾輩は、人の目を盗んで利用させていただく。農家には恨まれ、駆除されそうになるが、観光客は吾輩をめでてくれる。人間どもは日本猿と交雑個体を見た目で区別できないようだが、吾輩は住民と観光客を姿と振る舞いと殺気で見分ける。人が猿の加害度を測るように、吾輩も、人に吾輩の敵と味方がいることを認識し、島で遭遇した人の「加害度」を見極めて、ふるまいを百八十度変えることを学んでいる。環境省と農水省の猿害対策は前途多難のようだが、今のところ、吾輩の人間管理は順調である。
【謝辞】 原稿執筆にあたり、京都大学の渡邊邦夫名誉教授の助言を参考にしました。
また、原稿執筆にあたり、参考とした情報を以下の個人サイト
https://ecorisk.web.fc2.com/FACTA-Froricking-Animals.html
に掲載しています。
【編集部より】本連載は不定期に掲載します。