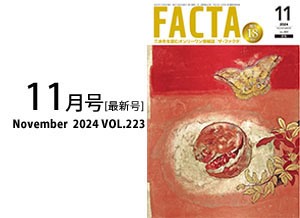アステラスの「首切り屋」の功罪/杉田副社長はやり過ぎか/改革を焦って組織が疲弊
外部から招き入れた改革者が評価体系や企業文化だけでなく、組織までぶち壊してしまったら元も子もない。
2025年5月号 BUSINESS

「一気に変える」がモットーの杉田勝好副社長
アステラス製薬が「改革疲れ」に陥っている。同社では杉田勝好副社長が先頭に立って人事改革とリストラを断行してきた。22年度に大所帯となる国内営業部門の給与体系にメスを入れたのも束の間、翌年度には早期退職を募集して400人近くを整理した。
ただ、あまりにも急ピッチで改革を進めた反動で社内には不満が蓄積。岡村直樹社長の耳には「次から次へといろいろなことが変わっていくので、本当にみんな疲れてしまった」との声が届いているという。新薬開発も遅れて株価は低迷。そこに社員の不満が溜まり、アステラス製薬の足元はぐらついている。
外資系製薬では訴訟沙汰
もともと山之内製薬と藤沢薬品が合併して05年4月に誕生したアステラス製薬は、3月末で発足から丸20年を迎えた。人間ならすっかり大人。二十歳となって人格ならぬ、ひとつの企業としての文化が醸成されたのか、一昔前のように「あいつはY(山之内)、あいつはF(藤沢)」などと、出身母体による派閥争いを聞くことも少なくなってきた。
一方で、初代社長の竹中登一氏や二代目社長の野木森雅郁氏の時代に掲げられた「世界トップテンをめざす」という志の高いスローガンも聞かれなくなり、企業文化は保守的になった。
原因は合併当初から続く減点方式の評価体系にあり、社員が失敗を恐れるあまりにチャレンジングな目標設定がされなくなったため。統合による混乱を最小限に抑えるために導入された評価体系だったようだが、結果として合併時の期待とは裏腹に、保守的文化の醸成に一役買ってしまった。
この評価体系を見直そうとしたのが前社長の安川健司氏で、「失敗を恐れずに挑戦する」企業文化をめざして改革を試みた。そこで招聘されたのが、英系製薬アストラゼネカの日本法人や日本マイクロソフトなど、外資系企業の人事責任者として辣腕を振るった杉田氏だった。
杉田氏の招聘は、グローバル企業としてより成長するために、ドメスティックな人事制度を改める狙いがあった。合併時から続いてきた評価体系をぶち壊して企業文化まで変えようというのだから、そこには一定の強引さがなければ不可能。一昔前に比べて派閥の壁は薄くなったとはえ、山之内と藤沢という旧2社のしがらみからか、古く硬直化したシステム・プロセスが残っていた。
もはや、外部から改革者を招かなければ変われない部分があったようで、そういう観点から見れば杉田氏は適任といえた。
ただ、杉田氏は製薬業界では「首切り屋」として知られる人物でもある。アストラゼネカでリストラを断行したことで名前が知られるようになった。アストラゼネカでの手法は強引で、営業部門に成果主義を徹底させた評価制度を導入したところ、不当評価や降格、賃金ダウンが相次ぎ、さらに退職強要があったとして労働組合との紛争に発展。社員が東京地裁に訴訟を起こす事態となった。
裁判は18年に社員側の事実上の勝利で和解が成立したが、杉田氏は裁判終結前に退職してしまい、その後、日本マイクロソフトの人事本部長を経て製薬業界に舞い戻ってきた。
杉田氏は21年5月に人事部門長に就任すると冒頭に述べた改革を次々と打ち出した。「アステラスは、やや保守的なカルチャーを持ち、行動が固定的になりがち」と指摘して、古参社員にプレッシャーをかけた。「どんどん改革するときに改革してしまわないと、なかなか変わらない」との考えから、人事制度を「一気に変える」と宣言。ペースについていけない社員をふるいにかけた。
アステラス製薬の目下の課題は、主力品である前立腺がん治療薬「イクスタンジ」の特許が27年から各国で切れることにある。イクスタンジは、同社の24年度第3四半期累計の売上収益1兆4530億円の約半分を占めるドル箱。特許切れの前に新たな稼ぎ頭となる新薬を確保する必要がある。そこで約8000億円もの巨額買収を通して加齢黄斑変性治療薬「アイザーヴェイ」を獲得。しかし、期待通りに開発がいかず、欧州での販売承認申請は取り下げ。減損損失約1160億円を計上してしまい、24年度の通期業績予想を大幅に下方修正する羽目となった。
アステラス製薬は決算発表が迫るたびに下方修正をするのが「お約束」となっており、今回で5期連続となる。アナリストから「常に減損のリスクに晒されるということは、会計上からも決して健全な姿ではない」と戒められるほど。
株価は新薬開発の躓きや、繰り返される下方修正への疑心暗鬼から低迷している。年初に1500円台でスタートした株価は、4月上旬には1300円台にまで下落した。時価総額は2兆5000億円程度で、25年度を最終年度とする中期経営計画で掲げる7兆円に遠く及ばない。一方、中計では販売管理費を20年度実績の売上比率31%から21%まで縮小することを掲げている。当然ながら、人件費のカットが視野に入っていた。
改革疲れ、組織が疲弊
ただ、あまりに急ピッチで人事改革を推し進めた結果、社内では経営陣に対する不信感が蓄積している。同社が全世界の社員を対象に実施した調査(24年10月時点)によると、「私たちは経営陣を信頼している」との設問のスコアが前年に比べて2ポイント下がった。さらに同社が「率直で正直なコミュニケーションを行う」との設問は4ポイントマイナス。「従業員と十分なコミュニケーションをとっている」との問いは6ポイントも低下し、最も下げ幅が大きかった。
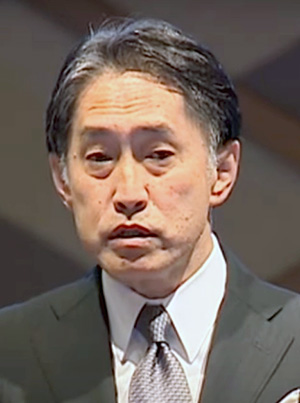
足元がぐらつく岡村直樹社長
調査結果は2月に同社開催のサステナビリティ・ミーティングで公表したが、岡村社長は経営陣への信頼が低下した結果に「嬉しいかと言われれば嬉しくない。非常に真摯に受け止めている」と表情を曇らせた。アナリストからは「かなりびっくりした。自分だったらショックだ」と言われる始末。岡村社長としては、前社長の安川氏から引き継いだ改革路線を推し進めているつもりかもしれないが、急ぎ過ぎた改革で組織が疲弊してしまった。
岡村氏は「組織にダメージを残したり、ケイパビリティを失ったりしないように注意しながら進めていく」と語り、改善に取り組む方針。また、杉田氏は「従業員の理解を深める対応が十分でなかった」と弁解に追われた。人事、デジタル、広報のメンバーを中心にタスクフォースを結成し、変革に関するコミュニケーションを強化する計画という。
ただ、すでに同社では経営陣への不信感や将来性に見切りをつけ、優秀とされた社員の流出が散見される。外部から招き入れた改革者が評価体系や企業文化だけでなく、組織まで破壊してしまっては元も子もない。このままナタを振るい続ければ、社員の士気が下がり続けるのは明白だ。
6月には株主総会を控えるが、新薬開発の遅れに株価低迷、さらには中国当局に2年前にスパイ容疑で拘束された同社社員の身柄が相変わらず解放されないなど、暗い材料ばかり。社員だけでなく、株主の信頼をどう回復するか課題は山積している。 改革を焦って転びそうなアステラス製薬だが、「首切り屋」としての杉田氏の同社での仕事も潮時ではないか。経営陣への信頼低下を回復するためにも、交代を検討する時期にきている。