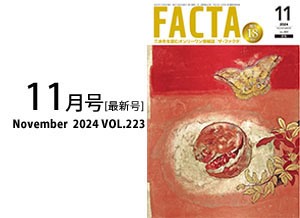三井住友建設「明日なき窮状」/主力行の三井住友が「白眼視する」本当の理由
麻布台ヒルズでのトラブルが尾を引くが、三井、住友の両グループとも救おうとしない。
2025年5月号 BUSINESS

旧三井建出身の柴田社長は、旧住友建出身の君島前会長と諮って社長の座を手に入れたとされる
Photo:Jiji
業界16位の準大手ゼネコン、三井住友建設が追い詰められている。2019年に森ビルから受注した超高層マンション「麻布台ヒルズレジデンスB」(東京・港)で施工トラブルが頻発。25年3月期まで4期連続で計上する損失の累計が750億円超に達し、昨年春には経営陣の内紛による社長解任劇も起きた。同業他社との合併・統合も噂され、旧村上ファンドによる株の買い増しも進んでいるが、旧財閥系の寄り合い世帯で求心力も技術力も乏しい同社は孤立無援の状態が続いている。
前田建や西松建と再編案
三井住友建設の施工トラブルで最も奇異なのは損失発生から3年以上経過し、累計損失も単一工事で前代未聞の規模に膨らんでいるのに具体的な施工案件を公表していないこと。ニュースリリースなどでは一貫して「2022年3月期から工事損失を計上している国内大型建築工事」との表現で通している。
本誌23年6月号(麻布台でババ引く「三井住友建設」)が麻布台ヒルズB−1街区のタワーマンションが当該工事であることを報じ、他媒体も徐々に明示するようになったが、それでも未だ案件名を明かさないのは「発注者である森ビルへの配慮」(業界関係者)とされる。
ただ、社運を賭した大規模プロジェクトを2年以上も停滞させられた発注者の怒りをそんな「配慮」で収められるのか。三井住友建設は22年3月期~25年3月期に計上した損失の累計757億円(予想)について「(発注者に支払う)違約金も全て織り込まれている」としているが、関係者は「違約金が膨らむ可能性はある」と見る。
これに対し証券市場では「百億単位の巨額損失を出している工事名を明かさないのは不誠実」「株価下落で損失を被った株主をはじめステークホルダー(利害関係者)への情報開示責任をどう考えているのか」といった投資家サイドからの疑問の声が絶えない。株主の不満に応える形で23年11月に弁護士や大学教授をメンバーとする同社の第三者委員会が調査報告書をまとめたが「営業秘密が含まれる」として全文を開示しなかった。
19年8月に森ビルが発表したプロジェクト概要によると、「麻布台ヒルズレジデンスB」は地下5階・地上64階建て、高さ約270メートルに達し、タワーマンションでは日本一の高さとなる見通し。延べ床面積約18万5300平方メートル、総戸数約970戸の住宅棟で19年8月に着工し、23年3月末の竣工を予定していた。
着工前から難工事が予想され、中でも地下部分は東京メトロ日比谷線と南北線がすぐ近くを交差するように走り、さらに地形の凹凸で地下5階まで掘り下げる設計になっていた。「三井住友建設はマンション建築では定評があったが、こんな深い地下工事は未経験だったのでは」と同業他社の幹部は推測する。
「麻布台ヒルズ」のオフィス棟であるメインタワー(高さ約330メートル)は大手ゼネコンの清水建設が受注し、当初は住宅棟も併せて一括受注するとの観測もあったが「ただでさえ森ビルの工事は採算が合いづらい。欲張らない方がいい」との声が上がって見送ったという。
一方、三井住友建設は「日本一高いタワマン」という“勲章案件”欲しさに当時の社長、新井英雄(70)らの首脳陣が約50人のプロジェクトチーム(PT)を立ち上げ、「特命案件」として受注活動を進めたという。だが、このPTはチーム内外の情報共有が不完全だった上、工事の懸念事項に対する詳細な検討がなされていなかった。
着工後には案の定、大深度の地下工事で大幅な工法変更を余儀なくされ、工期短縮を狙って導入した急速施工工法では使用されたプレキャスト部材に深刻な不具合が発生した。施工図の誤りで柱鉄筋貫通孔の位置がズレる初歩的なミスも発覚。「経験不足に検討不足が重なった」と業界関係者は解説する。
当然のことながら巨額損失で財務は大打撃を受けた。レジデンスBの受注額は「少なくとも600億円以上」とみられ、既に25年3月期時点で損失額が受注額を上回っているもよう。自己資本(連結)は損失計上前の20年3月末の957億円から24年12月末は608億円に減少、自己資本比率(同)は27.1%から13.4%に急落している。
自力再建に黄信号が点滅する中、主力行の三井住友銀行や所管の国土交通省では「この際、業界再編の突破口に」との声が上がり、一部では前田建設工業(業界11位)や西松建設(13位)といった他の準大手に合併・統合を持ちかけているとの極秘情報も流れている。
だが、人手不足が一段と深刻化し、一昔前までのように「ゼネコンの1+1は2にならない」との警句は通用しなくなったとはいえ、「あの会社はどうも……」と芳しくない評判がネックになっている。
バブル崩壊で行き詰まった三井建設と住友建設が合併し、三井住友建設が発足したのは03年。そこに至る過程で三井建は01年に1630億円、住友建は02年に300億円のそれぞれ債務免除を受けた“前科”がある。三井建は和歌山の土建業「西本組」が前身で戦後三井の資本を受け入れて三建工業、三井建設と商号を変えてきた。一方、住友建は愛媛の別子銅山で土木工事を請け負っていた「別子建設」が前身。二木会(三井系)や白水会(住友系)といった旧財閥系企業の社長会では「どちらのグループでも“孤児”のように冷遇されてきた」(関係者)。
銀行出身社長を追い出した
加えて、三井住友建設に支援の手が伸びないのは2つの理由がある。1つは巨額損失計上で経営の屋台骨が揺らいでいる渦中に経営陣の内紛が勃発。麻布台案件の赤字で引責辞任した新井に代わり、23年4月に社長の座についた三井住友銀行出身の近藤重敏(59)が翌24年2月に退任し、後任には三井建出身の取締役常務執行役員だった柴田敏雄(62)が昇格した。この唐突な社長人事は住友建出身の会長(当時)である君島章兒(69)と柴田が気脈を通じて仕掛けたとされ、旧三井建、旧住友建のプロパーが結託して銀行OBを駆逐した構図となった。
もう1つは旧村上ファンドの存在。村上世彰(65)の長女である野村絢(37)や南青山不動産(東京・渋谷)などが三井住友建設の株を買い進め、25年3月時点で26.97%を保有する大株主となったほか、子会社の三井住建道路の5.01%の株式を旧村上ファンドが取得したことも明らかになっている。アクティビストに攻められる同系ゼネコンの苦境を主力行の三井住友銀行が静観しているのはこの2つの理由が背景にある。迷走は当面続きそうだ。(敬称略)